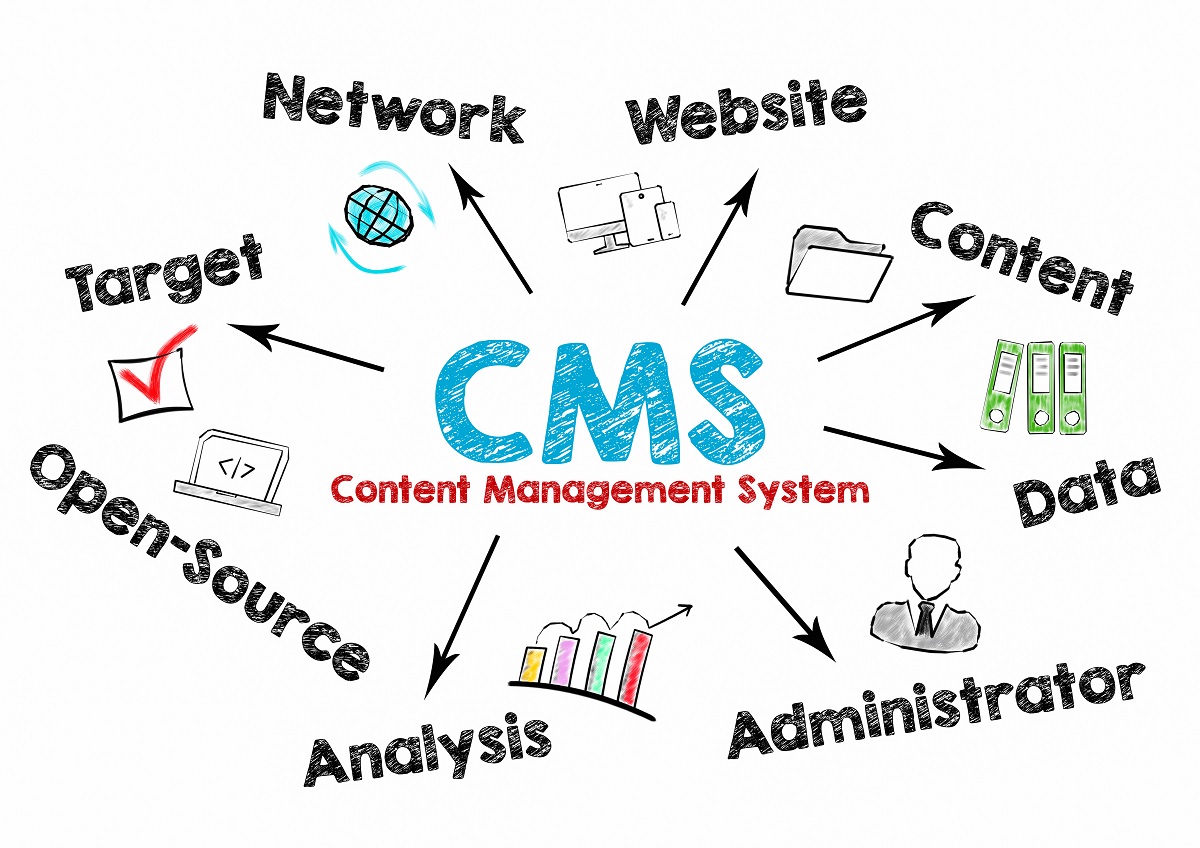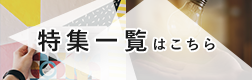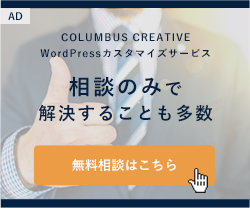コンテンツマーケティングにおける「ネタ・アイデア」が浮かばない時の注意点
- columbusproject
- Photo:
- 2021-08-17
コンテンツマーケティングを運営する中で「ネタ・アイデア」に枯渇するタイミングがあります。
しかし、無闇に方向性を変更したり、テーマやジャンルの裾野を広げてしまうと「一貫性」や「まとまり」のないメディアになってしまうので注意しなくてはなりません。
今回はコンテンツマーケティングで「ネタ・アイデア」が浮かばない理由、そしてネタ・アイデアが思い浮かばない時の注意点についてお話します。
コンテンツマーケティングで「ネタ・アイデア」が浮かばない理由
はじめにコンテンツマーケティングで「ネタ・アイデア」が浮かばない理由について解説します。
企業および組織におけるメディアとしての目的・用途に縛られるため
コンテンツマーケティングでネタ・アイデアが浮かばなくなる理由として、企業および組織におけるメディアとしての目的・用途に縛られることが挙げられます。
ユーザーに有益である情報であるとともに、ブランドイメージやコンテンツマーケティングの目的と乖離し過ぎるべきではないことが、ネタ・アイデアの制限になり、結果として発信する情報が限られてしまうということです。
目的や用途自体がメディアとしての記事コンテンツ制作に向かないため
コンテンツマーケティングの目的や用途自体が、メディアとしての記事コンテンツ制作に向かないこともネタ・アイデアが浮かばない理由になりがちです。
実際に自社の得意とする分野、蓄積されてきた技術・経験、業界や業種によっては情報の範囲・裾野を広げにくく、深堀りしにくいことがあります。すると、一定の記事数をアップした段階で、書く事がない、深堀りしようがない、話題を広げようがないという状況に陥ってしまうのです。
商品やサービスに関連するキーワードやテーマに対する視野が狭いため
コンテンツマーケティングの運営方針によっては、をネタ・アイデアの前提として、商品やサービスに関するものを選びがちです。もちろん、間違ってはいないのですが、商品やサービスへの関連のみに絞り込んでしまうと、キーワードやテーマに対する視野が狭くなってしまいます。
完全に関係のないキーワードやテーマを用いることはおすすめできませんが、商品やサービスだけでなく、自社の知見・技術・経験・人材など、企業や組織活動全体に関連させた方が視野が広くなることも覚えておくべきと言えます。
ネタ・アイデアが思い浮かばない時の注意点
次にネタ・アイデアが思い浮かばない時の注意点をご紹介します。
無闇に方向性の変更や裾野を広げすぎないこと
ネタやアイデアが思い浮かばない時、無闇に方向性の変更や裾野を広げてしまうことで、結果的に情報が浅く、質が低いサイトとして評価を下げることになりかねません。
コンテンツマーケティングの強みは「継続的に新鮮な記事をアップできること」であり、ドメインパワーやサイト自体の評価を育てられることでもあります。一貫性や統一感を意識しながら、ネタやアイデアが思い浮かばないとしても、無闇に方向性の変更や裾野を広げ過ぎることは避けましょう。
記事コンテンツ制作の担当者や部署・部門のみで解決しないこと
ネタやアイデアが浮かばない時にありがちなのが、いわゆる属人化です。特定の担当・部門・部署など限られた人数で記事コンテンツを作成していては、いずれ枯渇するということです。
そのため、ネタやアイデアが思い浮かばない時に担当・部門・部署で解決しようとせず、全社的にネタやアイデアを募集するなどして、ネタやアイデアを集めるのがおすすめです。考える人が増えれば増えるほどネタやアイデアに困ることはなくなります。
SEOやアクセスも大事だが「ユーザーに有益である」という点を忘れないこと
ネタやアイデアが思い浮かばないタイミングでは、SEOやアクセスばかりを気にしてキーワードやテーマ、方向性に悩むことがあります。
コンテンツマーケティングの基本は「ユーザーに有益である」ことを忘れている状況でもあり、ユーザーを置き去りにしているのは間違いありません。あくまでも記事コンテンツが認知・興味関心であり、購入や課金の分母を増やすことだと理解しておきましょう。そのためにも記事コンテンツを作る側もコンテンツ制作を楽しむこと、ユーザーが記事コンテンツを楽しんでくれることに注力することも忘れないでください。
まとめ:企業や組織全体でコンテンツマーケティングを運営するイメージが大切!
今回はコンテンツマーケティングで「ネタ・アイデア」が浮かばない理由、そしてネタ・アイデアが思い浮かばない時の注意点についてお話しました。
コンテンツマーケティングは企業や組織における「最終的な利益や売上をアップする」という目標が存在します。言い換えれば、記事コンテンツによって認知・興味関心を引き出し、自社の商品の購入やサービスへの課金を期待するものと言えるでしょう。
だからこそ、記事コンテンツ制作の担当者や部門・部署のみで解決しようとせず、企業や組織全体でコンテンツマーケティングを運営するイメージを持つことが大切です。ネタやアイデアも一人、または複数人で考えるより同じ企業や組織で働く人から募ることで思い浮かばないタイミング、枯渇してしまったタイミングで解決できるようになります。全社的に協力しながら、長く継続的にコンテンツマーケティングによるメディアを運営できる体制を整えることをおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事がコンテンツマーケティングでネタ・アイデアが枯渇、もしくは思い浮かばない時のお役に立てれば幸いです。